ぶっこみ釣りで狙う

数ある釣り方の中で初心者の人にもっともお勧めしたいのがこのぶっこみ釣りです。なんでウキ釣りなどではなくぶっこみ釣りなのかといいますと、
- 仕掛けがシンプルでとっつきやすい
- 高度なテクニックがいらない
- いろいろな魚が食ってくるので楽しい
というのがその主な理由です。
ややもすると、ただ仕掛けを放り込んでおくだけの釣りだと思われがちですが、そうでもありません。
私の「やや攻撃的なぶっこみ釣り」を是非お試しくださいませ。
違いはどのあたりかと言いますと、
- 誘いをかける
- 竿を持つ手から“気”を送る
ここらへんでしょうか。気を送るというのは、
「魚はいね~が~。いたらこっちこ~い(なまはげ風)」
ってな具合に竿から糸を通じて海の中にオーラを送り込むことになります。
効果のほどは・・・まぁまぁです。(ホントかよ)
シンプルな仕掛け
ぶっこみ釣りで使う道具は、
- 道糸
- 中通しオモリ
- ゴム管
- ヨリモドシ
- ハリス、針

これしか使いません。これらをつなげれば仕掛けは完成です。ちなみにゴム管は道糸とヨリモドシの連結部分を保護する役目で、中通しオモリに内蔵されているものもありますよ。
針は市販されているハリス付きのもので十分です。非常に簡単ですよね。
でも手の込んでないこんな仕掛けでもちゃんと釣れてしまいます。まずはこのシンプルな仕掛けを一連の動作の中で素早く作れるようになることが第一ステップでしょう。
釣りを始める前の注意点
※(磯竿の場合) 釣り座を構えたらまず竿を伸ばす前にガイドに糸を通してオモリ、ヨリモドシを先にセットしましょう。そしてリールのベールを起こしフリーの状態にして穂先から伸ばしていくのが楽で、時間のかからないやり方です。
先に竿を伸ばしてからガイドに糸を通していくのは、長竿ですと面倒ですしリールが地面に着いて傷がついたりもしますので避けたほうが賢明です。
また、穂先を伸ばすときはリールがフリーになっているのを確認しましょう。糸が出ない状態で伸ばしていきますと「ポキン」となって終了してしまうことがあります。
高度なテクニックがいらない

ぶっこみ釣りはエサをつけてドボンと放り込んでおけば後は魚のご機嫌次第・・・という風には私は考えていません。
何年も通った釣り場で、「ここには必ず魚が回ってくる」という確信があればほったらかしのぶっこみ釣りでもよいですが、初心者の人には無理な話です。
なので竿は置くのではなく手に持ち、穂先だけではなく手のひらでもアタリを感じましょう。
ですがただ竿を持っているだけでは面白くありません。魚にエサの存在をアピールするのです。
俗に言う「誘う」というテクニックです。
しかしテクニックとは言ってみましたが、たいそうなものでは全くありません。定期的に竿を少々起こすなりして、海中の仕掛けを引っ張ってやるだけです。
そうしますとオモリが海底を引きづりますので砂煙があがりますし、エサ自体も動きます。
好奇心の強い魚は「おや、なんだろう?」と思って近づいてくるわけですね。
そうすれば近くにエサがあるわけですから「ゴンゴン」とか「ブルブル」とかいったアタリが手元に伝わってくるというあんばいです。
また誘っている最中竿が重たくなったら、海底が傾斜状になっている「かけあがり」というポイントである可能性が高いので、しばらく待って様子を見てみましょう。 これは海底が砂地であるときに威力を発揮します。
引っかかるポイントでは誘わない
反対に、石や根が多い釣り場では頻繁に誘うと根がかりが多発してしまいますので、あまり誘わないのが手です。すでに魚の住処の近くに仕掛けが入っているわけですからね。
もし誘うときは、仕掛けが根の上を飛び越えて移動するぐらいの感じでやるとよいです。
一見地味で簡単なこの誘いなのですが、ほったらかしよりももちろん釣果はあがりますし
なにより「釣れた」のではなく「釣った」「食わせた」という攻めの姿勢に意味があるのではないかと思います。
また、ぶっこみ釣りといっても必ず仕掛けを投げなければならないわけではありません。
沖目に投げてどうも食いが悪いようなら、足元にスルスルと仕掛けを落としてもよいしハリスを短めにしてテトラや根周りを探ることもできます。
向こうから来てくれないなら、こちらから相手のいる所、いそうな所にエサを持っていってやりましょう。
いろいろな魚が食ってくる
ぶっこみ釣りはオモリでエサを底の方に沈めますので、中層や表層を泳ぐ魚を釣るのは難しいです。
しかし、オモリを軽くする、または外してしまえばミャク釣りやフカセ釣りにすぐチューンナップできますから、いろいろな魚を釣ることができるんです。
ある日、ちょい投げしてる海面を見てみたら15cmほどのカワハギとウマヅラが群れで浮いてきたことがありまして、すぐさまオモリを外して相手変更。そいつらを「見ながら釣る」なんてことをしたこともありました。もう取りあえず何か釣りたいんですね、私は。
それゆえ、「この魚だけを釣りたい!」という人には向いてない釣りかもしれません。
この世界には青物師、上物師、底物師などなど、これと決めた釣りしかしない人がいるのも事実です。
しかしそういった人たちも最初っからそれ一途だったとは限らないと思いますよ。いろいろな釣りを経験していくうちに取りつかれてしまったんだと思います。
私は釣りそのものに取りつかれてますから、大物狙いはもちろん、五目釣りやハゼ釣りも大好きですね。
それから、ぶっこみ釣りに限ったことではないのですが、たまにまったく想定外の魚が食ってきてびっくりさせられるのも面白いところです。
私が釣った想定外の魚たち BEST3
No.1 「30cmオーバーのメゴチ」
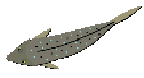
港内の短い突堤から何かいないかなーと糸を垂らしていたら来ました。ものすごい引きでした。ドキドキしながら上がってくる魚を見てみますとどうも本ゴチっぽいんですが、やたら口がとんがってるんですよね。
あれっと思いましたが釣り上げてみるとやっぱりメゴチで、初めてのサイズにびっくりしましたね。メゴチはしっぽが結構長い魚なのですが、それを差し引いてもデカかったです。
刺身でおいしくいただきましたよ。
ちなみにこれ以降今に至るまでこのサイズのメゴチは一度も釣れてませんので、あれは夢だったんじゃないかと思ったりしてます
No.2 「イセエビ」
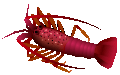
こちらは浜名湖の通称Tの字というちょっとした堤防から釣れました。夜だったのですが、モゾモゾしたアタリが長い間続きまして、どうもおかしいというわけで少し聞いてみたわけです。そうしましたら、一応食ってる感触があったので合わせました。
しかし、乗ってる感触はあるものの引きがないのです。巻いてる最中何度かククッと持っていくぐらいなものでした。ごみと小魚が一緒になってるのかななんて思いながら釣り上げてみてびっくり、なんとイセエビがひっついてました。もちろん刺身です。
ちなみに昔は赤羽根漁港のテトラ帯でイセエビを専門に狙ってる釣り人を結構見かけました。
短くてごつめの竿に両軸リールをつけてましたね。仕掛けはよく分かりませんが掛かったら有無を言わさずゴリゴリ抜きあげてしまうようです。
No.3 「イシガキフグ」
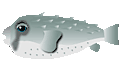
食べられないので第3位です。御前崎でウキを流していたときに来ました。けっこう大物だったのですが、ただただものすごく重たいやつでした。
上がって来たときにはバレーボールのように膨れ上がってて笑ってしまいましたね。
習うより慣れろ
一番最初は、竿やリール、その他の道具の扱いはもちろんですが、釣り自体に慣れることが大切だと思うんですね。
ぶっこみ釣りは、「投げる」「アタリをとる」「合わせる」「引きを体感する」「取り込む」など釣りの基礎となるものが詰まっていると思うのです。
釣りは知識で武装してもうまくいきません。(最低限の知識は必要ですが)
雑誌やネットで様々な情報を入手し、高級釣具や凝った仕掛けを持って釣り場に行っても、型落ちの竿、出来合いの道具しか持っていない地元の釣り少年には勝てないと思います。
また一連の動作もスムーズさに欠けるでしょう。
なのでまずは、釣行を重ねて経験を増やし、釣り用の体を作る事が 細かい知識を集めるより重要になってくるのではないかと思います。


